
こんにちは、primeNumberです。
去る9月16日、AI編集アシスタントサービス「StoryHub」が主催するイベント「StoryHub Communications Vol.4」がSmartNewsのイベントスペースで開催されました。
https://storyhub-communications-v004.peatix.com/
4回目となる今回のテーマは「AIが変える採用広報の未来」と題し、LayerX執行役員CHROの石黒卓弥さんが登壇。StoryHubのエバンジェリストである松浦シゲキさんが聞き手となり、AIを活用した採用・広報戦略の最前線について語られました
AIが記事作成を企画から仕上げまでワンストップで支援する「StoryHub」
イベント冒頭はStoryHub VP of Business高野政法さんがStoryHubについて紹介。ChatGPTやNotebook LMなど既存のサービスと比べて「企画から仕上げまでをワンストップで支援するツール」との違いを示し、一つの画面内で企画から構成、記事完成まで全ての工程を実行できる点がメリットだと説明。新聞社や出版社などの従来メディアに加えて、企業のオウンドメディアなど100以上のメディアに導入されていると語りました。
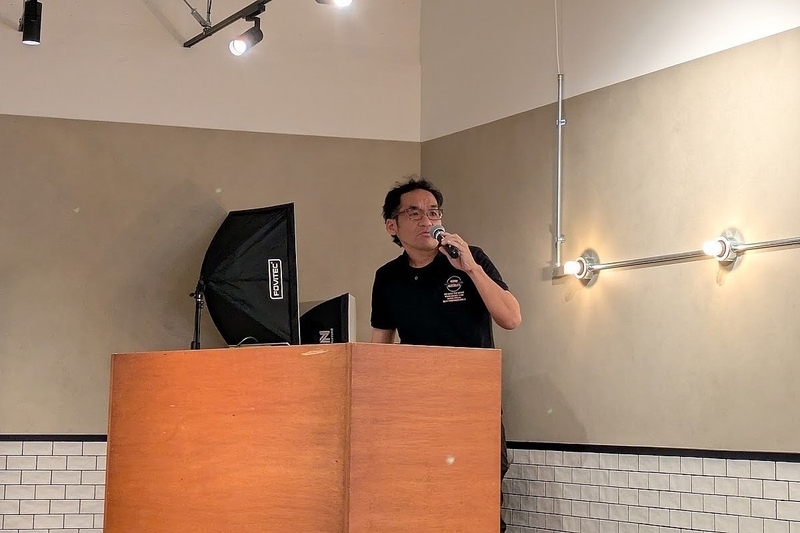

具体的な活用事例として紹介を受けた人事担当の方からは、自身が担当しているオウンドメディアでの活用法を紹介。「オウンドメディア業務に充てられる時間は全体の10%程度」という内情を明かした上で、「通常インタビューの記事化は一週間程度かかるが、StoryHubのおかげでインタビュー終了から24時間以内に記事化できた」と、大幅な効率向上が実現できたメリットをアピールしました。
StoryHub代表取締役CEOの田島将太さんは今後の機能拡充について説明。StoryHubにアップロードした素材と原稿を照合して事実に間違いがないかを確認する「素材ファクトチェック」を9月末、インタビューの文字起こしだけでなく、インタビューの質問もAIが対応してインタビュー記事作成を支援する「インタビューアプリ」を11月頃にリリース予定です。
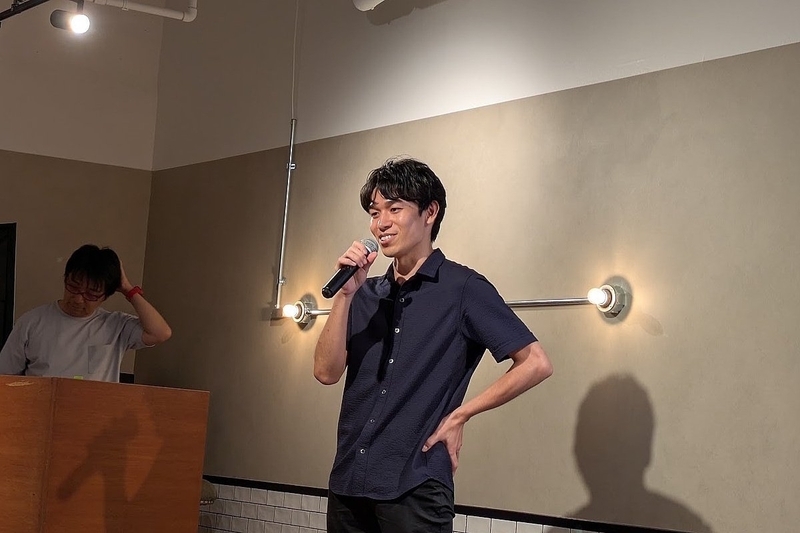


AI活用のポイントは「トップがコミット」と「全員で共有」
メインセッションとなる「AIが変える採用広報の未来」では、AIや広報、採用をキーワードにした9つのトークテーマから司会進行の松浦さんがトークテーマを選び、石黒さんが答えるという形で進行しました。

松浦さんが最初に選んだのは「LayerX 人事チームのLLM活用最前線」。石黒さんは「弊社は採用活動に関するポリシーを公開していて、AIだけで判定しないことを明記している」と断った上で、応募があると履歴書情報や文字情報などをAIが判定して書類選考の提案をする仕組みがあると紹介。
LayerXでは新卒採用でもAI面接を活用しており、「私の時代には考えられなかったが、AI面接なら大学生が23時や25時に1次面接を受けられるというのはやってみての学び」と語りました。

マネージャーの立場では360度フィードバックのコメントで「相手が誤解を与えたり、不要に傷つく表現になっていないかをAIにチェックしてもらえる」という使い方も紹介。「面接の内容もAIがまとめてくれるので、面接の中キーボードを触らなくてすみ、候補者に集中できるようになった」と自社のAI活用を語りました。
逆に組織浸透において苦労したポイントを松浦さんが質問すると、石黒さんは「LayerXはAIカンパニーなので、AIを使うことに抵抗がある人がまずいないんです」と回答。「重要なのはトップがコミットすることで、リーダーシップチームが意識的に使うようにしている」と、上の人が率先してAIを活用していくことが重要だと語りました。
社員の間でAIの使い方に個人差が出るのでは、という質問には「うまくいっている人の事例をみんなででシェアすることを大事にしています」とコメント。8月に開催した「Bet AI Day」という大型AIカンファレンスでは49人がLTを発表、その中にはエンジニアだけでなく、ビジネスサイドやコーポレートのメンバーも参加していたそうです。
https://tech.layerx.co.jp/betaiday-links
石黒さんは「LayerXの社員400人のうち49人なので、1割近くが事例を共有したことになる」と説明、「チャットツールをはじめAIの利活用は個人の中で閉じがちですが、それを可視化して社内で共有していくことがとても大事」と共有の重要性を説きました。
全員広報のポイントは「ハードルを下げる」「発信を称賛」「プロ目線でフィードバック」
続くトークテーマで松浦さんが選んだのは、LayerXが掲げる「全員広報」戦略について。

石黒さんは「全員広報については過去なんどか取材を受けているので、ChatGPTに聞いたら答えてくれるのでは」とした上で、「重要なのは、限りなくハードルを下げることと、みんなの発信をちゃんと称賛していくこと、そしてHRやPRのプロの目線でフィードバックをすることが大切」と回答。「外にアウトプットすることの品質は一定の水準にする必要があり、LayerXでは基本的には広報のチェックを通すようにしています」という情報発信のための社内フローを紹介しました。
質と量のバランスについて松浦さんが質問すると「質か量で悩んでいる時点で『まず1本出そう』という話」と一刀両断。「めちゃくちゃ量を出すか、めちゃくちゃ質にこだわるか、まずはどちらかに振った方がいい」と情報発信の重要性を語った上で、「炎上が怖いかもしれないが実際にはそう簡単に燃えないのでは」と補足しました。
LayerXは毎月ニュースリリースやオウンドメディアの記事を月平均で70~80本、平均で1日4本と非常に多くの記事を公開していますが、石黒さんは「営業やカスタマーサクセスエンジニアなど、記事によって読みたい人が限られるので、ボリュームがある分には悪いことはない」と説明。「質については、世の中がちゃんと判断してくれる。読まれるものは本当に1本で500favがついたりするので、一旦どちらかに振ってみることが大事」とアドバイスしました。
全員広報に続く「全員採用」についても、広報と同様「リーダーがやっている背中を見て皆さんがアクションを取るということが、全員広報や全員採用につながっています」と、上の人がまずアクションすることの重要さをアピール。
また、採用の意識を合わせるための社内コミュニケーションも重要視しており、毎週行う全社会議でHR担当が今必要な職種を100秒でアピールする「今週のHot JD(=Job Description)」という企画を紹介。「HRが『営業が欲しい』と言っても、広告営業、SaaSの営業、エンタープライズ営業では全然違う。『一例だが社内の○○さんみたいな人』という具体例を示すことで、外向けの採用メッセージだけでなく、社内メンバーの解像度を上げています」と企画の目的を示しました。
トークテーマの最後は「LayerXで採用広報・採用担当として働くメリット」。石黒さんは「最先端の情報が集まる、見晴らしの良いポジションにいる」と自社を評価し、「社内にはAIの専門家が多くいますし、HRや広報でも尊敬できる人が本当に多い。大きな課題を解くために良い環境ができていると思います」としました。
以前に石黒さんが所属していたメルカリも全社一丸の採用活動を行っていますが、石黒さんは「メルカリのようにこの年代を代表する会社として「あの時の人事や広報が面白かった」と言われるようなものを作っていけたら面白いと思っています」との思いを語り、「自分たちで新しいものを作ろうという仕事ができる環境なので、そういった環境を考えたい方がいらっしゃったら、ぜひご紹介いただけると嬉しいです」と呼びかけました。
Q&Aコーナーでは参加者から質問へ石黒さんが率直に回答
セッションの後半は参加者からの質問に石黒さんが答えるQ&Aコーナー。「悪い口コミを書かれて採用で苦労しています」という質問には「事実でないものについてはプラットフォームごとにちゃんと申請をする」という正攻法に加えて、「膨大な発信をすると分母が大きくなるので、膨大な発信をすること」「反論すると燃え上がるので気にしない」との対策も紹介。
また、「ストレートに返して恐縮ですが」と断った上で、「書かれた理由に対して真摯に向き合い、フィードバックとして受け止めた上で、社内で変えられるものを変えながら量で凌駕していくのも1つのやり方だと思います」とのアドバイスを送りました。

「AIで社員を削減する動きもある中、LayerXは積極的に採用しているが、どういうロジックで意思決定しているのか」という質問は、「LayerXはまだ作るプロダクトが大量にあり、それを届けるセールスも必要なのでソフトウェアエンジニアと営業はまだまだ採用していきます」との方針を示しました。
最後に「若い人や新卒に向けた発信で意識されていることはありますか」という質問には「動画にすごくシフトしている」とコメント。「数年前はGoogleで検索していたが、今の若い人はYouTubeやChatGPTで検索している。彼らの検索結果に出ないのは致命的なので、この半年間すごく動画に注力しています」と、常に新しいプラットフォームを積極的に試す重要性を説きました。
イベントを通じて、AIを全面的に活用しながらも人間にしかできない判断や創造性の価値も重要視するLayerXの方針は非常に学びになり、採用や広報だけに限らない、AIの活用に悩む多くの企業の参考となるモデルケースだと感じました。
AI-Readyを掲げ全社でAIを推進するprimeNumberも、LayerXの事例に学びながら、AIによる効率化と人間による価値の創造を目指していきたいと思います。貴重な機会をいただいた登壇者の石黒さん、そして運営の方々、ありがとうございました。
